2023年度 · 2024/01/27
2024年1月27日(婦選会館)
▽基調講演
「2024年度予算、国・自治体はどう動く」
菅原敏夫さん(元 地方自治総合研究所)
▽講演
「横須賀市におけるデジタル・ガバメント推進の取組み」
松本 敏生さん(横須賀市 経営企画部 ICT戦略専門官)
▽ 講演
「これからの都市計画とまちづくり」
窪田 亜矢さん(東北大学大学院教授)
2023年度 · 2023/12/09
日本は、COP28にて12月3日、岸田首相のスピーチを受け、石炭火力発電所を延命することに対して化石賞を受賞、さらに同5日、日本は再び化石賞の対象となった。気候変動対策に関して、取り組む姿勢が後ろ向きで国際会議の中でも足を引っ張っている。
二酸化炭素濃度は、産業革命以降に急激に上昇している。世界の平均気温は1890年から1℃以上上昇しており、主な原因として温室効果ガスの排出が挙げられ、代表的なものが二酸化炭素である。今後何も対策をとらなければ、2100年までに最大5~8.5℃上昇する。人類にとって、危険な気候を回避するために、1.5℃の上昇に抑えることが、世界共通の課題となっている。気候変動の影響は、自然界における影響だけでなく、インフラや食料不足など人間社会を含めて深刻な影響が想定される。
2023年度 · 2023/11/11
2013年設立のNPO法人ピルコン(Program for Ideal Life Communication & Networking)は、「誰もが自分らしく生き、性の健康と権利を実現できる社会」をビジョンとして、「性の健康と権利について誰もが気軽に学べる、語り合える、相談でき、支援につながれる環境の実現」をミッションとする。SNSによる発信を活用しながら、中学・高校生向けのプログラム(ピア・エデュケーション)をはじめ、保護者やPTA向けの講演、政策提言、人材育成、教材作成や情報発信、自助グループ運営や相談支援などの活動を行なっている。
2023年度 · 2023/10/28
2023年10月28日(婦選会館)
▽基調講演
シングルマザーの困難と女性の人権
小森雅子さん(社会福祉士、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)
▽講演
女性に困難を抱えさせない健康福祉政策とは
早乙女智子さん(産婦人科医、ルイ・パストゥール医学研究センター研究員)
▽ 講演
年収の壁にどう取り組むか
西沢和彦さん(日本総研理事)
▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円)
2023年度 · 2023/10/14
<外国人の定住を認めない日本>
現在の日本には400万人以上もの外国移住者や外国ルーツを持つ人々が暮らしているが、「外国人」への人権侵害が横行する。朝鮮から強制連行され、戦後、帰国せずに日本に残った人々への差別は変わらず、1980年代半ば以降に急増したアジア諸国からの出稼ぎ労働者たちは使い捨てられ、90年代にはブラジルなど南米の日系人の就労が合法化された。
さらに、途上国への技能移転を建前とする制度がなし崩しに拡大され、2000年代以降、技能実習生が40万人にも達した。厳しい制約を受ける技能実習は「強制労働」だとの内外からの批判も強く、ようやく制度見直しの議論が進行中である。
2023年度 · 2023/09/09
吉良智子さん(日本女子大学学術研究員)は近代日本美術史・ジェンダー史を研究しており、この講座のテーマ(戦争と女性画家たち)については2013年より3冊の著書を出している。すでに1、2冊目は品切れとなり、2023年7月に加筆した3冊目が『女性画家たちと戦争』として刊行された。テレビなど、メディアでも注目されている。
2023年度 · 2023/08/04
日時 2023年8月4日(金)10:15~16:00
会場 婦選会館<対面式>
▽映画上映
「原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち」
▽基調講演
岸田政権の原発回帰政策の問題点
松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)
▽ 自治体からの報告
・トリチウムの放出が生業をうばい取るかも
及川幸子氏(宮城・南三陸町議)
・東日本大震災から12年 岩沼の今とこれから
布田恵美氏(宮城・岩沼市議)
2023年度 · 2023/07/08
<世界の食料安全保障>
これまで世界的な食料危機は10年に1度くらい発生しており、その原因として、異常気象、人口増加と経済成長、バイオ燃料需要の拡大、先物市場の投機資金増大、輸入超大国となった中国の動向などが挙げられる。
2020年以降のパンデミック(新型コロナウィルス感染症)は新たな危機をもたらした。世界的なサプライチェーンが混乱し、とりわけ低所得国では飢餓人口が急増した。さらに、ウクライナ紛争(2022年2月〜)は主要な食料輸出国同士の戦争であり、安価な小麦の輸入に頼る低・中所得国に深刻な影響を及ぼしている。東アフリカの干魃もある。
2023年度 · 2023/05/27
2023年5月27日(婦選会館)
▽基調講演
「子ども・若者の声を聴いて…」~地域(栃木)に広がる子ども若者支援
中野謙作さん((一社)栃木県若年者支援機構代表理事)
▽講演
スマホ世代の子どもとどう向き合うか~SNS 、ゲーム、ネットいじめの問題を考える
石川結貴さん(ジャーナリスト)
▽ 講演
保育の質を考える~保育の環境・保育士の労働条件・保護者支援
手塚 崇子さん(川村学園女子大学教授)
2023年度 · 2023/05/13
長年、フルタイムの仕事の傍ら、ボランティアとして、こどもや女性を支援する活動に携わってきた。コロナ禍によって、居場所のないこどもや暴力に晒される女性は、ますます困難な状況に直面させられており、新たな仕組みづくりが求められる。支援活動の担い手の育成も必要だ。
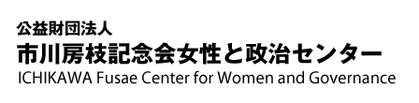
住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-21-11 婦選会館
TEL: 03-3370-0238
FAX:03-5388-4633
E-mail:fitikawa@trust.ocn.ne.jp
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
Copyright ©ICHIKAWA Fusae Center for Women and Governance. All Rights Reaserved.
Copyright ©ICHIKAWA Fusae Center for Women and Governance. All Rights Reaserved.










