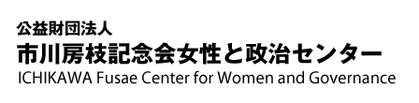不妊治療の低い成功率
「不妊」とは、学会の定義によれば「妊娠を希望し、1年妊娠しない場合」だが、結婚年齢の上昇を背景に、1年を経過せずに治療に入ることも多い。男女どちらが原因でも、あるいは原因不明であっても、不妊治療は女性に大きな身体的な負担を強いる。しかも、成功率がきわめて低い事実が知られていない(1回の体外受精では3.7%、最初に採取して凍結した卵を使う胚凍結によって24.1%)。そのため、当事者たちも周囲も過度に期待するが、毎月、結果が出てしまうため、精神的な負担は計り知れない。にもかかわらず、不妊治療への保険適用という少子化対策は、経済的な側面のみの支援にとどまる。また、そもそも「不妊治療」と言うものの、これは病気の治療ではなく生殖技術なので、不妊を受け入れない限り決心がつかず、不妊治療を止めることが難しい。
第三者のかかわる生殖技術と子どもの出自を知る権利
一旦、卵を体外に出して人工授精させてから戻すという生殖技術の発達は、他の女性の子宮に受精卵を戻すことも可能にした。1980年代以降、こうした第三者がかかわる様々な生殖技術が可能になり、90年代には各国で新しい生殖技術に関する法制化が進んだものの、その内容は国によって異なる。
日本では、2003年、厚生科学審議会・生殖補助医療部会が報告書を出した。「生まれてくる子の福祉を優先する」「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」「安全性に十分配慮する」「優生思想を排除する」「商業主義を排除する」「人間の尊厳を守る」を理念として、精子、卵、胚の提供と、生まれた子どもの出自を知る権利を認める一方、代理母・代理出産を禁止する方向性が示された。しかし、子どもが出自を知る権利に反対し、代理出産を認めるよう主張する国会議員の反対により、法制化が頓挫してしまった。2020年、僅かな審議時間で成立した生殖補助医療法は、理念なき立法であり、15項目もの付帯決議を伴う。規制は盛り込まれず、今後2年間の検討に委ねられている。
AID(非配偶者間人工授精)で生まれた子どもは、国内外でかなりの人数に上り、年齢層も広いが、ようやく当事者として語り始めた。AIDによる出生が本人に隠され、親の病気や離婚など家族の危機に際して、事実を知ることが多いため、二重のショックを受ける。「騙していた」親への怒りとともに、自分は何者なのかという悩みに直面する。国連・子どもの権利条約に照らして、出自を知る権利は、養子ばかりでなくAIDの場合にはなおさら、生まれてくる子どもの福祉を最優先して、認められつつある(北欧諸国、英、豪など)。日本社会においては、そうした視点が弱いのではないか。
出生前診断の現状
日本の産婦人科では、超音波(断層)診断が頻繁に、しかも、本人の同意を取らずに行われているという問題がある。胎児細胞を分析する羊水診断は1970年代から使われている。その後95年頃から企業主導による胎児の異常の「確率」を求める絨毛診断、あるいは、新型出生前検査とされる母体血中胎児由来(cell-free)DNA検査(2011年開始、日本では限られた施設で臨床研究中)も、確定には羊水診断が必要とされる。また、体外受精の場合、胚移植するかどうかを判断する着床前診断の検査方法も網羅的になっており、日本では2004年から臨床応用されている。
女性の基本的人権としてのリプロダクティブ・ライツ/ヘルス
国家による人口政策は、増減いずれであっても、女の性と生殖が対象となる。例えば、日本では戦時中の「産めよ殖やせよ」および1990年代以降の少子化対策、開発途上国における強制的な不妊手術・避妊、そして、先進国の移民、先住民、障がい者への不妊手術・避妊の強制が挙げられる。こうした国家とそれを支える男性中心の家父長制による人口政策・生殖管理への抵抗として、性と生殖の自己決定権が、女の主体性を取り戻すための女の健康運動として展開されてきた。
1970年前後のウーマン・リブ運動では、「産むことの強制からの自由」を求める避妊・中絶の合法化が中心課題であったが、1980年代には、強制的な不妊手術・避妊政策に対して「産まないことの強制からの自由」も提起された。いずれも強制されるべきでないことを明示したのが、「性と生殖に関する権利」と「性と生殖に関する健康」を合わせて意味する「リプロダクティブ・ライツ/ヘルス」である。この言葉は、1994年、カイロ国際人口会議の行動計画に盛り込まれ、国連・北京世界女性会議(1995年)において、女性の基本的人権として確認された。
「リプロダクティブ・ライツ/ヘルス」とは、妊娠・出産だけでなく生涯を通じての性と生殖の権利と健康である。女性の自己決定権は、女性の社会的位置づけや関係性から制約を受けやすい。選択して決定できるためには、情報と手段を利用できることがきわめて重要である。
しかしながら、日本の現状は、その情報と手段が欠如している。刑法(1880年)の堕胎罪の規定(1907年)がいまだに生きている。その上、優生保護法(1948年)は母体保護法(1996年)に改められたが、中絶を決められるのは医師であり、「本人及び配偶者の同意」が条文にある。そのため、DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けた女性や配偶者がいない場合には、必ずしも「配偶者の同意」を要しないことを厚生労働省が認めているにもかかわらず、実際には、中絶しにくく、妊娠を継続して女性のみが非難される事態が跡を絶たない。
また、日本における避妊方法はコンドームへの偏りが著しく、ピルへの拒否感が強いだけでなく、多様な避妊方法が使えず、新たな避妊方法の公開や認可にも時間がかかる。他方で、避妊よりも先に優生保護法が中絶を認可しながら、掻爬法が定着してしまい、WHO(世界保健機関)が初期中絶について標準とする吸引法は普及しない。妊娠11週までの中絶薬も認可されない。しかも、生殖医療を規制する法がないまま、小規模の不妊治療クリニックが乱立し、技術や経験が蓄積されずに、高額な医療費を請求される。
すべての人にとって、リプロダクティブ・ライツ/ヘルスに関する情報と手段は不可欠であり、それは男女を問わず、ともに自分と相手を大切にする性教育、多様な生き方ができる社会的な仕組みにまで及ぶのである。(眞)
【イベント詳細】2021連続講座「進めたい「いま」、弾力ある社会へ」
| 講師 |
2021年6月12日(土)13:30〜15:30 「生殖技術の発達とリプロダクティブ・ライツ」 長沖暁子さん(慶應義塾大学講師) |
| 形式 |
オンライン(zoomウェビナー) |
| 参加費 |
1,100円(税込) |
| 定員 | 50名(要予約) |
【メッセージ】「不妊治療や出生前診断など生殖技術の発達によって、女性の妊娠出産をめぐる状況は大きく変化している。不妊治療への保険適用が検討され、課題を2年後に積み残した生殖補助医療法が制定されるなど、少子化対策として政策的にも焦点があてられている。このような状況は女性の性と生殖に関する権利/リプロダクティブ・ライツにどのような影響を与えているのだろうか。すべての女性にとってのリプロダクティブ・ライツとはどのようなことなのか考えたい。

【プロフィール】生殖技術の発達と女性の自己決定権に関心を持ち、生まれた子どもを含めた当事者への調査研究を行ってきました。共編著に『AIDで生まれるということ-精子提供で生まれた子どもたちの声』(萬書房、2014年)などがあります。