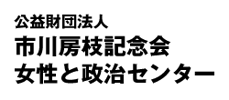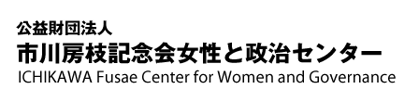24年度第3回の政治参画フォーラムが10月26日に行われた。
1.基調講演「自治体の福祉政策と地方財政」
地方財政審議会委員 星野 菜穂子氏
1) 地方財政計画歳出の推移をみると、一般行政経費の伸びは高く、2000年には
20兆円だったが、2010年に30兆円、2020年には40兆円を超し、2024
年には44兆円に至り、社会保障の増大を反映している。一方、歳入のうちの
一般財源の方は、2000年の58兆円から2008年に60兆円となったが、そ
の後は足踏み状態が続き、2024年の65兆円まで緩やかな伸びにとどまって
いる。
2) 一般財源は、地方税、地方譲与税、地方交付税などで、地方自治体が使途を決
められる財源であるが、令和4年度の決算統計から自治体の福祉財政の姿をみ
ると、目的別歳出では民生費が37.2%、性質別歳出では扶助費が24.2%と大
きく伸びている。
3) さらに、民生費の内訳としては社会福祉費72,676億円、老人福祉費42,751
億円、生活保護費36,806億円に対し、児童福祉費は94,537億円に至る。
4) これらは、2015年以降の「子ども・子育て新制度」によるもので、子ども家庭庁の新設も相まって、政府の主要施策となったといえよう。
5) 新制度の下での国・地方の負担割合は以下の通り。
国 都道府県 市町村
ア.子どものための教育・保育給付費負担金(原則)1/2 1/4 1/4
イ.施設型給付 公立幼稚園・公立保育所 10/10
ウ.地域型給付(公私共通) 1/2 1/4 1/4
エ.子ども・子育て支援交付金 1/3 1/3 1/3
(うち利用支援事業は2021年より引上げ) 2/3 1/6 1/6
オ.子育てのための施設等利用給付 1/2 1/4 1/4
カ.児童手当(2024年10月以降)
被用者3歳未満:支援納付金3/5、事業主2/5
非被用者3歳未満:支援納付金 3/5、国4/15、地方2/15。
被用者及び非被用者3歳以降:支援納付金1/3、国4/9、地方2/9
6) 今後も、地域社会の変容により福祉はますます重要になる中、自治体が福祉政策を展開していく上でのポイントは、
・地域ニーズの把握の重要性。地域として施策を推進していくこと。
・サービス供給には、自治体だけでなく、NPO法人、住民等を巻き込んだネッ
トワークの構築。
・地方自治体が主体だが、国の動向も注視。
・一般財源に注目➡自治体が自由に使える財源の安定的確保が重要。

2.講演「地域における『多文化共生』を考える」
国士館大学教授 鈴木 江理子氏
1)受け入れるにあたっての2つの外国人政策
①移動局面における外国人政策(国境通過にかかる政策)
「好ましい外国人」と「好ましくない外国人」の線引きによる国境管理政策
②居住局面における外国人政策(国境通過後の政策)
受け入れた外国人の社会保障、政治参加、住居、労働、教育、言語などに関す
る政策
例:同化政策、多文化主義政策、統合政策、多文化共生政策
2)多文化化はどんどん進んでいる
・在留外国人数は急増している。
・1990年1,100,000人➡2007年2,300,000人、この年以降1位は中国
人。➡2024年3,589,000人、195の国と地域からの外国人が在留。
・1952年以降、累積で60万人近くの外国人が日本国籍を取得している。
これに伴って、「ダブル」と呼ばれる日本国籍の子どもも増加しており、2023
年、日本で出生届が出された日本人の子どもの2.1%(15,120人)がダブル
の子どもである。
・今や、日本で生まれる子どもの22.5人に1人が外国ルーツの子となっている。
日本財団の2021年の調査では、小学校に外国ルーツの子どもがいたとの回答
者は3割に至っている。
3)こうした現状から判るように、国の外国人政策は変化している。
・1)①で示したように、わが国では、長く移動局面の外国人対策が中心であり、
外国人労働者はいわゆる「単純労働者」で、その受入れの是非が論点だった。
・しかし、今後は居住者、そして社会の構成員として外国人に対して個々の行政
分野の断片的な関与ではない総合的な外国人行政を行っていく必要があると示
されている(第二次出入国管理基本計画2000年3月)
4)しかし、依然として外国人にとっての不平等が存在する。
・制度上の不平等~義務教育からの排除➡不就学の子ども
外国人学校への公的支援の欠如➡外国人学校に通う子ども
・子どもたちの多様性への対応の遅れ~国籍、母語、来日時期、日本以外の国
での教育状況、今後の滞日予定etc
・親の就労状況など家族に起因する問題~不安定な収入、頻繁な転勤、失業、
複雑な家族関係
5)「不平等」を解消し、「おなじ」を実現するための処方箋は「ある」
・「壁」を超えること~言葉の壁:情報の多言語化、日本語学習支援
~制度の壁:差別的な制度的不平等の是正
~心の壁:実質的不平等の是正、差別禁止法の制定
・「壁」を超えるためには、社会経済的格差の是正が必須である。
~①統計データの整備や意識調査による実態把握、
②格差是正のための優遇措置の導入

3.講演「発達障がい者支援の現状と課題~精神保健福祉士として、職員として」
市川市職員・日本発達障がいネットワーク理事 渡辺 由美子氏
1) 発達障がいの定義と特性
主なもの
・注意欠陥多動性障害(ADHD)集中できない。じっとしていられない。一方
で過集中。話が止まらない。衝動的(考える前に動いてしまう)➡行動力につ
ながることがある。
・自閉症巣ペクトクラム症(ASD)以前は知的な遅れを伴うと考えられていた。
興味関心の偏り。パターン化した行動で落ち着く。極端な器用・不器用。
対人関係や社会性に課題がある。感覚の過敏さ・逆に鈍さ。過集中も。
・学習障がい(LD)「読む」「書く」「計算する」といった能力が、知的な発達に
比して、極端に苦手。
例:ディスレクシア:教科書をすらすらと読めない。似た形のひらがなが
うまく書けない。
・トゥレット症候群 チックを主な症状とする症候群。すばやく繰り返される
運動や音声。
2) 災害時の発達障がい児・者支援についての対応のコツ
健康状態や心身の疲れを確認しましょう。
からだ~発達障がいのある人は、体調不良やケガがあるにもかかわらず、本人
自身も気づいていない場合はある。周囲が気づかずそのまま放置する
と状態悪化につながるのでていねいな観察と聞き取りが必要。
・気づくための観察例:息切れ、咳などが頻発でないか。
:やけどや切り傷、打撲などがないか。
:着衣が濡れていても着替えないでいるか。
・気づくための質問例:いつもより寒くないですか?
:歩くときにふらふらしませんか?
:服の着替えがありませんか?
ストレス~なにげないことでも、発達障がいのある人には日常生活に困難を来
すぐらい苦痛に感じることがある。そのためストレスの蓄積が起き
やすく、支援を優先的に考えなければならない場合がある。
・気づくための観察例:配給のアナウンスがあっても、反応が遅かったり、ど
こへ行っていいか分からず困っていることがないか。
:耳ふさぎや目閉じなど、刺激が多いことで苦しそうな
表情をしていないか。
・気づくための質問例:配給に並ぶ場所はわかりましたか?
:ほかの場所(避難所内外)へ移動したいという希望
はありますか?
◎対応に協力してくれる人が周囲にいるかどうか確認しましょう。(規)

市川房枝政治参画フォーラム2024 共に生きる ~一人ひとりが尊重される社会へ
【主催者メッセージ】
自治体の抱える課題解決には財源の視点が重要です。特に福祉政策を進めるための「地方財政」の視点に着目します。また、多くの外国人就労の状況下、生活習慣、学校教育の対応なども含め、「共に生きる」「多文化共生社会」とは何かについて深めます。発達障害については5月フォーラムでの学びを一歩進めます。専門家として行政の相談に携わり、発達障害を代表する全国組織の理事として活動し、専門家でもある講師に具体的な施策と課題を学びます。多くのご参加をお待ちしています。
| 日時 | 2024年10月26日(土)10:00~16:15 |
| 会場 | |
| 講師 |
▽基調講演
自治体の福祉政策と地方財政 ▽講演
地域における「多文化共生」を考える ▽ 講演 発達障害者支援の現状と課題 ~精神保健福祉士として、家族として 渡辺由美子さん (市川市職員、精神保健福祉士、日本発達障害ネットワーク理事) ▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円) |
| 参加費 |
現職議員12,000円・現職議員以外5,000円 〈音声(CD)受講:1コマ3,000円+送料〉 ※お振込方法は本ページの最下部にございます |
| 定員 | 約40名(要予約、受付先着順) |