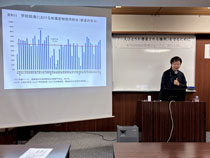2025年度 · 2025/10/25
2025年10月25日(婦選会館)
▽10:10~12:10 基調講演「女性支援法施行の意義と課題―地方自治体の役割を問い直す」
お茶の水女子大学名誉教授、女性支援法推進を促進する会会長 戒能 民江さん
▽13:10~14:40 講演「私の意思」を尊重した支援とは~官民協働の支援の必要性~」
国立市政策経営部市長室長 吉田徳史さん
▽14:45~16:15 講演「困難に直面する女性との関わりから見える必要な『手』」
NPO法人mia forza 門間尚子さん
▽16:30~17:30 交流会(自由参加)
2025年度 · 2025/05/24
2025年5月24日(婦選会館)
▽基調講演 「 こどもの健やかな育ちのために」
竹内和雄さん(兵庫県立大学教授)
▽講演「給食無償化 ―子どもの食格差とセーフティーネットの構築―」
鳫咲子さん(跡見学園女子大学マネジメント学部教授)
▽ 講演「 デジタル性暴力ってなんだろう?―スマホ必携が進む社会で―」
内田絵梨さん(NPO法人ぱっぷす理事)
▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円)
2024年度 · 2024/10/26
2024年10月26日(婦選会館)
▽基調講演
自治体の福祉政策と地方財政
星野菜穂子さん(地方財政審議会委員)
▽講演
地域における「多文化共生」を考える
鈴木江理子さん(国士舘大学教授)
▽ 講演
発達障害者支援の現状と課題
~精神保健福祉士として、家族として
渡辺由美子さん
(市川市職員、精神保健福祉士、日本発達障害ネットワーク理事)
▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円)
2024年度 · 2024/05/25
2024年5月25日(婦選会館)
▽基調講演
「女性差別撤廃条約・日本審査へむけて」
林 陽子さん(弁護士・当財団理事長)
▽講演
「不登校が増える今、子どもたちに大人は何ができるか」
土橋 優平さん(NPO法人キーデザイン代表理事)
▽ 講演
「発達障害のある人への差別の禁止」
川島 聡さん(放送大学教授)
▽16:30~17:30 交流会(自由参加)
2023年度 · 2024/01/27
2024年1月27日(婦選会館)
▽基調講演
「2024年度予算、国・自治体はどう動く」
菅原敏夫さん(元 地方自治総合研究所)
▽講演
「横須賀市におけるデジタル・ガバメント推進の取組み」
松本 敏生さん(横須賀市 経営企画部 ICT戦略専門官)
▽ 講演
「これからの都市計画とまちづくり」
窪田 亜矢さん(東北大学大学院教授)
2023年度 · 2023/10/28
2023年10月28日(婦選会館)
▽基調講演
シングルマザーの困難と女性の人権
小森雅子さん(社会福祉士、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)
▽講演
女性に困難を抱えさせない健康福祉政策とは
早乙女智子さん(産婦人科医、ルイ・パストゥール医学研究センター研究員)
▽ 講演
年収の壁にどう取り組むか
西沢和彦さん(日本総研理事)
▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円)
2023年度 · 2023/05/27
2023年5月27日(婦選会館)
▽基調講演
「子ども・若者の声を聴いて…」~地域(栃木)に広がる子ども若者支援
中野謙作さん((一社)栃木県若年者支援機構代表理事)
▽講演
スマホ世代の子どもとどう向き合うか~SNS 、ゲーム、ネットいじめの問題を考える
石川結貴さん(ジャーナリスト)
▽ 講演
保育の質を考える~保育の環境・保育士の労働条件・保護者支援
手塚 崇子さん(川村学園女子大学教授)
2022年度 · 2023/01/28
2023年1月28日(婦選会館)
▽基調講演「2023年度予算、国・自治体はどう動く」
菅原敏夫氏(前 公益財団法人地方自治総合研究所委嘱研究員)
▽講演「2024年の介護保険」
小竹雅子氏(市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰)
▽講演「保険あってサービスなし!介護保険の近未来~介護保険改悪を防ぐために~」小島美里氏(NPO法人暮らしネット・えん代表理事)
2022年度 · 2022/10/23
◆医療保険制度の現状と課題
西沢和彦氏(日本総合研究所 調査部 主席研究員)
第二次世界大戦後における日本の社会保障は、社会保険制度を中心に据えてきた。負担(社会保険料の拠出)と受益(給付)との関係が明確な社会保険は、権利性とともに、拠出していなければ給付を受けられないという排他性も伴う。そのため、理念として掲げる医療保険についての「国民皆保険」(公的年金については「国民皆年金」)は、もともと矛盾を抱えている。
2021年度 · 2022/01/29
2022年1月29日(婦選会館)
▽講演「22年度 国、自治体予算のニューノーマル ―再配分と財政の役割」菅原敏夫さん(前 公益財団法人地方自治総合研究所委嘱研究員)
▽基調講演「子どもの貧困をめぐる政策」末富芳さん(日本大学文理学部教授)
▽ 講演「ヤングケアラーと官民連携の那須塩原市ヤングケアラー協議会の取り組みについて」仲田海人さん(作業療法士)
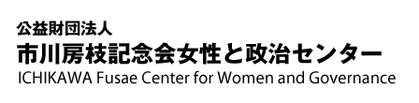
住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-21-11 婦選会館
TEL: 03-3370-0238
FAX:03-5388-4633
E-mail:fitikawa@trust.ocn.ne.jp
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
Copyright ©ICHIKAWA Fusae Center for Women and Governance. All Rights Reaserved.
Copyright ©ICHIKAWA Fusae Center for Women and Governance. All Rights Reaserved.