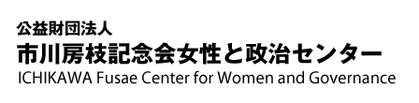2025年度1回目の政治参画フォーラムが5月24日に行われた。
1. 基調講演「 こどもの健やかな育ちのために」 竹内 和雄さん(兵庫県立大学教授)
society 5.0超スマート社会は、コロナ感染拡大で進み、AI 家電、キャッシュレスや無人走行バスなどが実現しつつある。ネットは、便利で楽しい面もあるが、危険や不安とも隣り合わせである。飲食店で迷惑行為を行い、動画をあげたために損害賠償請求された例や首相のフェイクニュースなど様々ある。法や制度がネットの普及や進化に追い付いていない。2歳児の6割以上がネットを使っている。学校でのネットによるトラブルは、社会の責任でもある。ネットで炎上するのは0.5%であり、学年にひとりいる計算となる。
学校でのいじめは、被害者と加害者が速い速度で入れ替わり、ネットを介して行われる。加害者は、朝食を食べていない場合が多く、保護者に朝食を作ってもらえないことに失望している。おとなにほめてもらいたい、話しかけて欲しい、学校行事を行って欲しいなどと考えている。相談できるおとなや窓口があることが重要である。ネットに手段が変わっても「心」が解決の鍵となる。(正)

2. 講演「 給食無償化 ―子どもの食格差とセーフティーネットの構築―」
鳫 咲子さん(跡見学園女子大学マネジメント学部教授)
・給食費未納問題 ・就学援助の限界と給食無償化 ・韓国の例から ・無償化とともに対象の拡大を の4つをテーマについてお話いただいた。
1. 給食費未納問題
文部科学省(以下 文科省)が行った最新調査(「平成28年度学校給食費の聴取状況に関する調査の結果」)によれば、学校が認識する給食費未納の主な原因は、「保護者としての責任感や規範意識」が7割、「保護者の経済的な問題」が2割を占めている。しかし、これは学校に対し行った調査であり、保護者や子どもの実態(ニグレクトの可能性もあり)を表しているかは疑問である。
全体の0.9%の小中学生が給食費(食材費)未納であり、このうち生活保護・就学援助の対象者は16%であるが、申請を行っていない場合もある。教育委員会と福祉部局の連携が十分でないため生じるミスリーディングがある。
学校の給食費会計は、公会計と学校毎で行う私会計があるが、私会計の学校が多く、未納給食費の督促は、学校管理職や学級担任が行っており教師の負担が心配される。無償化への課題の1つである。
2. 就学援助の限界と無償化の必要性
新型コロナウイルス感染症の影響で貧困層は大きな影響を受けた。学校給食がなくなり、生活保護、就学援助を受けてる家庭は学校給食費相当の支援は受けられなく、独自に支援した自治体もあった。コロナばかりでなく、現在の物価高や災害などの環境変化を貧困層特に一人親世帯は影響を受けている。
戦後学校給食法でき、中学校に拡大されたが、既に給食費未納が問題になっており、給食を普及するには経済的支援を行わないと未納は防げないということから就学援助制度ができた。
文科省のデータによれば、就学援助を受けている小中学生は2011年の16%をピークに下がり続け、2023年は13.7%になっている。県別にみると一番高い高知県は25.5%、一番低い山形県は7.1%であり、西高東低の自治体間格差がある。貧困層において、就学援助を利用しない理由として、「制度の対象外だと思う」が77.3%を占め、周知不足が伺える。学校給食の無償化は2026年から全ての小学校で実施される。
3. 韓国の学校給食無償化
韓国では朝鮮戦争終了後に学校給食が始まり、高校優先で無償化が始まった。
就学援助等による給食費支援という選別的福祉よりスティグマ(レッテル貼り)のない無償化である普遍的福祉を選んだ。無償化は給食をもっと美味しくという保護者の願いと、新環境濃産物(国産のオーガニック農産物)の利用を進める民間団体の運動もあり、首長選挙の争点にもなった。無償化の財源は基礎自治体と広域自治体(特別市、広域市、道)の教育・行政部門それぞれの協議で分担している。
地元産の新環境農産物を学校に使用することを支援する「学校給食支援条例」を制定してる。学校給食に供給される全農産物のうち新環境農産物は重量の49.8%、金額の53.4%を占める(推計値)。多くの自治体で一般の農産物との差額を支援しており、これに要する予算は2019年度で3,018ウォン(301億円)である。新環境農産物を食べる家庭、食べない家庭の格差をなくす役目をしている。
日本では学校給食における地場産物や国産食材の使用が推奨されているが、金額ベースで、山口県が87.2%と最も多く、大阪府が7.2%と最も低い。都市部は低い。
4. 無償化とともに対象の拡大を
文科省の調査によれば、夜間定時制高校の完全給食実施率は2026年の42.1%から2023年度は22.1%に減少してる。これは給食費をプリペイドカードを用いての前払方式であることが一因である。給食のある学校は中退率が低い。子ども食堂やフードバンクの利用率は、小中学生にくらべ低い。高校生にとっては敷居が高い。学校における無料の給食サービスを使ってみたいとする高校生は、46.7%に上りニーズは高い。
給食配食センターから配食している自治体では、少子化で余力があるところは高校や夏休み中の学童保育に給食を配食しており、ここから高校生への拡大を図ることができるとよい。貧困層における朝食の摂取状況は、週1~2回食べないが8.6%いるが保護者の健康状態が良くないケースはほとんど朝食を食べていないが18%を占める。
無償化とともに必要なことは、災害時などに、地域の食のセーフティーネットとしての機能を学校給食は果たすこと。少子化の中で、高齢者、高校生、学童保育への配食など地域給食の可能性を模索すること。保護者負担を軽減し、給食の質も向上させること。子どもの食支援のために地元農産物を活用すること。就学援助の周知を強化することをあげられた。(田)
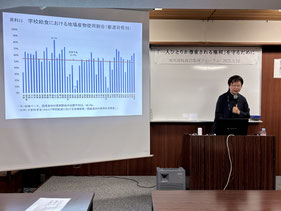
3. 講演「 デジタル性暴力ってなんだろう?―スマホ必携が進む社会で―」
内田 絵梨さん(NPO法人ぱっぷす理事)
NPO法人ぱっぷすとは、2017年11月設立したデジタル性暴力や性的搾取による被害の相談に応じている団体で、被害直後からの総合的な支援のため、4つの活動を行っている。
① 相談支援
② 人に変わって拡散した性的画像記録の削除要請を行う
③ アウトリーチ、居場所提供
④ 政策提言
デジタル性暴力とは、「性的同意」の自由がなくなって、自分の意志による写真や動画のコントロールができなくなる状態。写真を撮る、写真を持つ、誰かに見せる、取った写真やネットで見る、すべてが性暴力になる。
令和5年度総務省調査報告から、全年代では、スマートフォンの利用率が97.5%と高く、年代別でも各年代で90%を超過。水道の普及率と同等という。
どんな手法での被害かというと
1)グルーミング(子どもに近づき信頼を得て、その罪悪感や孤立感などを利し、関係性をコントロール(支配)する
2)セクスティング(性的な会話、自画撮りの要求、ビデオ通話の録画)
3)セクストーション(ATMでお金支払えなど脅し)
リベンジポルノ(性的画像を拡散)
加害を可視化するため、グルーミングの加害実態調査を実施し、その結果、2023年グルーミングに関する法律が新設された。
金銭セクストーションは急速にエスカレートする脅威だが、まだ対策をしていない日本の若者がターゲットにされている。
被害者への対策として、1文字たりとも情報を送らない、即ブロックなどの対応で被害者を孤立させない。しかし、被害をなかったことにし、被害者を追い詰め、声を挙げさせない仕組みがある。
「自己責任」にさせない社会を作るには、
1)性的同意・デジタル性暴力の認知度向上
情報や出来事を正しく理解し、単なるITスキルではなく、法的・倫理的な判断能力のインターネットリテラシーが必要だが、性的同意やデジタル性暴力を知らないと理解や判断ができず、無意識のうちに加害行為を行ってしまう可能性もある。
2)人の気持ちに思いを馳せる(想像力を育む)
自分の行動がどう影響を及ぼしていくのか、相手はその時どう思っているのか、相手の気持に思いを馳せるための想像力を育む必要がある。
自分の権利を主張することが大事
自分が守られる法律がある 証拠を味方につける 専門機関に相談
意に反して拡散した性的画像記録の削除(ソーシャルワークの視点から削除)
2019年度17,389件 → 2021年度 21,876件 (約70%削除)
削除要請における撮影された側と撮影者・消費者の格差
撮影された側 匿名性が担保されていない
撮影者・消費者 匿名性が担保されている
最後に
性暴力は寂しさや不安からの支配欲
教育委員会や先生方にもデジタル性暴力について話を聞いてほしい
行政作成のチラシにも掲載し駅やトイレに置く
「相談してもいい」という認識をより広げるために、人と人とが「繋がること」が大切
多くの方々にデジタル性暴力被害について周知していくことが必要である。(山)

市川房枝政治参画フォーラム 2025 「一人ひとりが尊重される権利」を守るために
| 日時 | 2025年5月24日(土)10:00~16:15 |
| 会場 | |
| 講師 |
▽基調講演 「 こどもの健やかな育ちのために」 竹内和雄さん(兵庫県立大学教授) ▽講演「給食無償化 ―子どもの食格差とセーフティーネットの構築―」 鳫咲子さん(跡見学園女子大学マネジメント学部教授) ▽ 講演「 デジタル性暴力ってなんだろう?―スマホ必携が進む社会で―」 内田絵梨さん(NPO法人ぱっぷす理事) ▽16:30~17:30 交流会(自由参加・要予約・茶菓代500円) |
| 参加費 |
現職議員12,000円・現職議員以外5,000円 〈音声(CD)受講:1コマ3,000円+送料〉 |
| 定員 | 約40名(要予約、受付先着順) |
| 申し込み方法 | フォーム、メール、FAX、電話でお申し込みください。 |